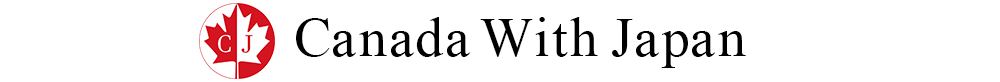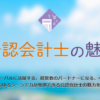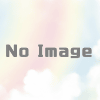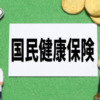東京都協力金 受付開始! 中小事業者の方々へ50万円 or 100万円給付されます。
感染拡大防止協力金
2020年04月22日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部から「東京都感染拡大防止協力金」の受付を開始します!と発表がありました。
感染拡大防止協力金とは感染拡大防止に協力してくれた中小事業者の人には給付金をあげますよ!という制度です。
この記事は東京都の公式ホームページまたはそこから飛べるリンクを元に作成されています。
一番初めにする事は?
専門家による事前確認が円滑な申請と支給に繋がる為、まずは専門家に相談する事を推奨しています。
(対象となる専門家)
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
※これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、そ
の方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。
専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の
提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合
があります。

対象は?
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小事業者の方々。
レストランも対象内!
食事提供施設は社会生活を維持するうえで必要な施設と対象外となっていますが、「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設は今回の給付の対象内となっています。
対象施設一覧(令和2年4月17日19時00分)はここから確認してください。
期間は?
受付期間は令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで。
協力金の支給開始は5月上旬を予定しています。
支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
申請書類は?
- 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
- 誓約書
- 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
- 休業等の状況がわかる書類
- 支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は押印不要 登録可能な金融機関リスト
オレンジの書類は同じリンク内に申請用紙のリンクが張ってあります。
受付方法は?
オンライン提出の場合
ポータルサイトから提出できます。6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。

郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出できます。6月15日(月曜日)の消印有効です。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
宛先
〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出できます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
都税事務所・支所所在地
開庁時間は8時30分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)です。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。なお、対面での受付・説明はございません。
都税事務所・支所所在地はこちらで確認できます。
分からない事があって区役所などに行っても対応して貰えないようです。協力金相談センターに電話で問い合わせるようにしましょう。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
まとめ
日本でも新型コロナの対策が進み、少しずつですが、実際にサポートを受けられる体制が整ってきたように思います。
今回世界中でそうですが、このパンデミックは今までに無い事態で各国新しい政策や法律を作り対応しています。
それは全てが正しいとは限らないのが、政府側の本音だと思います。
実際カナダでも様々な対策が行われていますが「チャレンジ」として、この危機を乗り越えましょうと呼びかけています。
日本は長い歴史がある為、いろいろと改善するにはすんなりいかないのが現状で不満も多いと感じます。
しかし、実際給付30万から一律10万に変わったように国民一人一人が真剣に声を上げればそれは変更される事もある!
マスクが配給されしかも不良品ばかり。。。さらにその後ろには麻生大臣の。。。など言葉にならない行動も引き続き起っており、いい加減にしてくれ!!と思う事も多々。
しかし、それをないがしろにせず改善するまで声を上げ続ける事は無駄な事では無いと私は感じます。


また都道府県だけでは無く、市区町村で各自対策、サポートをしています。是非一度お住まいの市区町村・都道府県のホームページなどを検索してみてください!